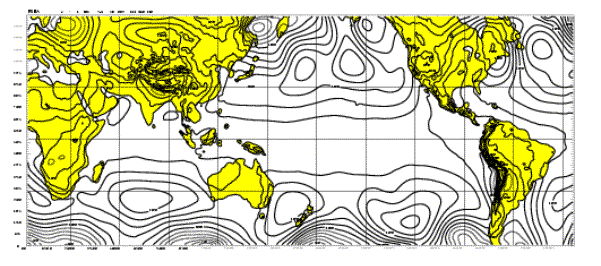1. はじめに
気象研究所予報研究部で開発された非静水圧モデル(Ikawa and Saito,
1991=Tech. Rep. MRI)は、その後、気象庁JSMやRSMとのネスティング(Saito, 1994=JMSJ; 斉藤, 1996=秋季大会予稿集)、マップファクターを含む完全圧縮方程式系への改良(Saito,
1997=Geo. Mag.)、物理過程の強化や新しい工夫の追加、などを経て、本格的メソスケールモデル”MRI-NHM”(斉藤・加藤, 1999=気象研究ノート)へと発展してきている。これまで、様々なメソスケール現象のシミュレーションや再現実験などの研究目的に応用されてきた他、近い将来の気象庁の現業用非静力学領域数値予報モデルについても、MRI-NHMをベースにした気象研究所・数値予報課統一メソモデル(MRI/NPD-NHM)の共同開発が始まっている(室井・他、1999=本予稿集)。
MRI-NHMでは、これまでネスティングに際して、初期値/境界値に気象庁領域モデルの予報値を用い、地図投影法としては、ポーラステレオ投影法を用いてきた。ポーラステレオ図法を用いた理由の一つとして、Saito
(1997) では、マップファクターmが1となる基準緯度j0を計算領域の中央にとることを前提に、
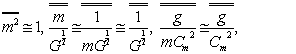
を仮定してインプリシット法のコーディングを簡略化していたことがあった。上記の仮定は、緯度別に海陸分布が大きく片寄る場所では厳密には成立せず、またマップファクターの平均値が1にならないケースや他の投影法でモデルを用いることが出来ない、という制約があった。
今回は、上記(50)式の近似を除去し、地球渦度の水平成分に対するコリオリ力も含む方程式系について、メルカトルやランベルトを含む任意の等角投影法に対応できるように手直しし、ネスティングランに必要な初期値/境界値の作成ユーティリティを整備した。また、従来の放射側面境界条件に加えて、境界緩和を併用できるように改良した。さらに、気象庁p面全球解析データを初期値・境界値に用いて、モデルを動かせるようにした。これらの改良は、MRI/NPD-NHMにも適用可能であり、今年度から始まっている気象研究所4次元データ同化システムの構築に向けて、ランベルト投影法を用いるRSMやMSMの領域解析/予報サイクルにNHMを使う試みや、メルカトル投影法が適している熱帯域や低緯度の台風のシミュレーションにとって重要である。またp面解析データからのネスティングは、気象庁がインターネット上で配信しているDDBデータを用いた外部機関でのNHMランが可能になるという利点がある。上記に加え、将来の気候研究への非静力学モデルの応用も想定して、計算領域を準全球スケールに拡大して長時間ランさせるテストを開始した。
2. 結果の例
1)斉藤 (1996) で示した1996年6月21日のTREXのケースについて、RSMにネストした水平分解能10kmのNHMが、3種類の投影法を用いて同じ結果を示すことを確認した(図略)。
2)6時間おきの1.25度の気象庁p面全球解析データを用いて、メルカトル投影法で領域を拡げた場合の例を下図に示す。水平分解能は緯度36度で125km、鉛直には38層をとり、最下層の分解能は40mで水平風の第1層は地上20mに位置している。領域は、全球の約3/4をカバーする南緯55度〜北緯60度で、モデル地形は高度6000mを超えるヒマラヤ山脈を含んでいる。降水過程はドライモデルで、海面水温・地面温度は今回の例では便法として最下層の大気の温度を代用している。
今後テストを継続し、モデルのパフォーマンスと問題点を調べていくつもりである。