1. はじめに
気象庁では、防災気象情報の高度化を目指して、現行MSMに代わる非静力学モデルの現業運用を計画している。このための現業数値予報用非静力学メソモデル(NHM)の開発が気象研究所と共同で行われている。
前回までの講演(斉藤2002a,b; 春季学会予稿集B307; 秋季学会予稿A305)では、NHMを、スプリットイクスプリシットスキーム (HE-VI法)を用いて水平分解能10km程度で時間刻みを30秒以上にして安定に動作させるためのいくつかの工夫(発散抑制フィルター、重力波・移流のタイムスプリット)について講演した。これらの改良により、計算安定性についての目途が立つようになった。今回は、領域平均気圧の保持に関する2つの変更について報告する。
2.浮力の扱い
NHMでは、密度rを単位体積当たりの湿潤大気と含まれる水物質(雲水、雨、雲氷、雪、あられ; 各々添え字c, r, i,
s, gで表す)の質量の総和で定義している。
Saito(1997;Geophys. Mag.)では、NHMの完全圧縮系化に際し、浮力BUOYを密度偏差から直接計算する手法を導入し、以下で定義した。

ここでσは密度の定義に関するスイッチパラメータで、σ=1のときは従来どおりに温位摂動から、σ=0のときには密度摂動から直接厳密に浮力を計算する。鉛直方向の運動方程式は
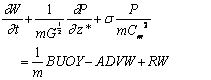
となって、σ=1のときは気圧摂動の項が生じる。
これまでNHMの場合、HI-VI法ではσ=0とσ=1のどちらでも扱えるようになっていたが、HE-VI法ではσ=1を仮定していた。σ=1の場合、鉛直1次元の楕円型気圧方程式の上下部境界条件にそのまま気圧摂動項が残るため、Lorenz型の鉛直スタガード格子では上下部境界でこの項の値を正しく決めることが難しいという問題点が生じる。これまでNHMでは、HE-VI法を用いたMSM領域を対象とする18時間の積分では、モデルの立ち上がり時に気圧が0-0.5hPaほど上昇し、積分期間中には、さらに0-1hPa程度上昇することが知られていた。この平均気圧上昇は特に冬場に顕著で、NHM現業化に向けての大きな問題点となっていた。
ここでは、上記の欠点を改善するために、HE-VI法に対しても浮力を密度摂動から直接厳密に求めることができるようにした。σ=0のときには気圧摂動の項は鉛直運動方程式中には形式的に生じないが、安定な時間積分を行うためには、浮力の気圧摂動寄与分をインプリシットに扱う必要がある。このため、鉛直1次元の楕円型気圧方程式の境界条件は形式的にはσ=1の場合と殆ど同様になるが、境界外の気圧決定精度に関する感度は鈍くなり、問題は顕在化しなくなる。ただし、σ=0の場合、重力波をスプリットするためには、密度を小さな時間刻みでも毎回計算する必要が生じる。
下図に2003年3月1日06UTCのメソ解析を初期値とする10kmNHMによるMSM領域18時間予報の平均海面気圧を示す。従来のσ=1としたNHMでは18時間予報後には境界値を供給するRSMの同領域平均気圧との差が1hPaを超えていたが、σ=0としたNHMでは、平均気圧はほぼRSMのそれに一致している。
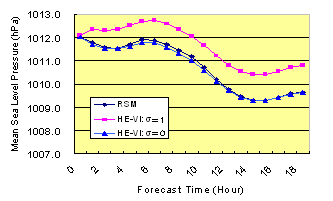
3. 連続式における水蒸気拡散の考慮
これまでNHMでは、密度が水物質の重みを含むことから、降水に伴う密度の時間変化を考慮して、
![]()
を連続式として用いていた。上式を体積積分することにより、領域平均気圧の時間変化に対する領域側面質量フラックスの総和と領域総降水量の関係が得られる。平均強度1
mm の降水は平均気圧で0.1 hPaの質量損失に相当するため、NHMでは領域平均降水強度をモニタし、側面境界の運動量を動的に調整している。この方法の問題点として、領域総降水量は領域総面積に比例する一方で側面境界は長さの次元に比例するのみであるために、領域が拡がるほど側面での運動量調整量が大きくなることがあった。
今回、この問題の改善策として、連続式において次のように降水落下による質量損失PRCに加え、水蒸気拡散も考慮することにした。
![]()
上右辺第2項は水蒸気の拡散で、ここでは乱流モデルに基く物理拡散のみならず、数値拡散(4次線形拡散、非線形拡散、2次適応水蒸気拡散)も含めている。上式の体積積分に基く側面質量フラックス調整は、領域平均降水強度と地表面(海面)からの水蒸気フラックスの差となる。両者は互いに相殺するため、調整量は小さくて済む。広領域では長期的には両者は釣り合っていることが考えられ、領域気候モデルとしての利用や将来的なNHMの全球化においては、重要な改良と考えられる。