1. はじめに
気象研究所の計算機システムは昨年3月に更新され、スーパーコンピュータはそれまでのS-3800からSR8000にリプレースされている。SR8000は36ノードの分散主記憶型並列計算機で、その機能を十分に発揮するためには、プログラム全体を並列化する必要がある。また、平成10年度より始まっている科学技術振興調整費研究に「雲解像非静力学モデルの最適化並列プログラム構築に関する研究」がある。この研究は、2002年に運用開始が予定されている地球シミュレータ上で動作する並列ソフトウェアを開発するためのもので、研究目標として、数千km四方の領域を対象に個々の雲を解像して降水過程を再現する高分解能並列非静力学大気モデルを開発し、地球シミュレータでの高速シミュレーションにより、集中豪雨・豪雪等の局地的顕著気象現象や台風の微細構造を再現する1kmメッシュ気象学を確立することを挙げている。前回の講演(斉藤ほか、1999=秋季学会予稿集B306)では、高度情報科学技術研究機構などとの協力で行われた気象研究所非静力学モデル98年版(MRI-NHM982)の並列化について、インプリシット気圧方程式解法の並列化手法を中心に報告を行った。今回は、その後行われた気象研究所非静力学モデル99年版(MRI-NHM997)の並列化と実行例について、簡単な報告を行う。
2.変更点
基本的な並列化手法は、前回と同様で、MPIを通信関数に用いて、全体領域を緯度(y軸)方向に分割して並列化している。MRI-NHM982からのモデルの主な変更点は以下のとおりである。
1)雲物理過程の雲水/雲氷量から直接大気放射を計算するスキームの導入(永戸ほか、1998=秋季大会予稿集B110)
2)ランベルト、メルカトル図法など、任意の等角投影法への対応(斉藤、1999=秋季大会予稿集P315)
3)SR8000への移行時にノード内自動並列機能(要素並列)阻害要因となったループ内サブルーチンコールの除去
4)数値予報課との統合モデル(MRI/NPD-NHM)としてのHE-VI計算スキーム(室井ほか、1999=秋季学会予稿集B305)への対応
(但し、このバージョンではHE-VI部分は未並列、HE-VI法の並列化効率については、室井ほか、2000=本予稿集を参照)
またMRI-NHM982の並列バージョンで未並列だった部分として、
5)静力学バージョン(Kato
and Saito, 1995=JMSJ)
6)移流補正スキーム(Kato,
1998=JMSJ)
の並列化も行った。さらに並列実行時のリスタートファイルの整備にも着手している。
3. 結果の例
SR8000に並列モデルを用いて1000km四方以上の領域を覆った雲解像シミュレーションとして、永戸ほか(1998=秋季大会予稿集B110)が報告した寒気吹き出し時の層積雲のケースについての計算例を図1に示す。モデルの大きさは (362×362×38)、水平分解能3kmで、warm rainを用いている。
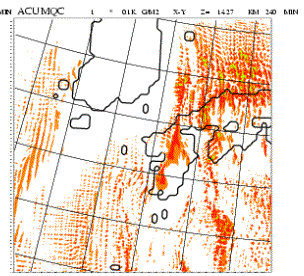
図1 並列モデルによる1997年1月22日06JSTを初期値とする4時間後の820m-2680mの積算雲水量。0.2Kg/m2以上に陰影(0.5Kg/m2以上は濃く陰影)。
4. 問題点と今後
気象研究所のSR8000の場合、メモリ的には、1000km四方の領域を、4ノードで2km分解能で、16ノードで1km分解能でカバーすることが可能である。但し、現時点では、並列化したモデルを用いて4ノードで実行しても、オリジナルモデルによる1ノードによる実行と比較して大きな計算時間の短縮には至っていない。並列化に伴うオーバーヘッドやオリジナルモデルでのチューニングが一部使えないことの他、SR8000ではノード内並列とノード間並列の競合の問題があるかも知れない。今後、さらに計算効率を高める必要がある。このモデルをベースとして、HE-VI法も並列化した統一モデルの開発が数値予報課との共同で進んでいる(室井ほか、2000=本予稿集)。今後は統一モデルの利用を柱にして、地球シミュレータでの運用を目標にした雲解像モデルとしての最適化を目指していく必要がある。
5. 謝辞
科学技術振興調整費研究「雲解像非静力学モデルの最適化並列プログラム構築に関する研究」は以下の担当者で行われている。
斉藤和雄・加藤輝之・吉崎正憲・瀬古弘・永戸久喜(気象研・予報)、上野充・村田昭彦・益子渉(気象研・台風)、室井ちあし(気象庁・数値予報=気象研・予報に併任)
プログラムの最適化に関しては、(財)高度情報科学技術研究機構の協力のほか、(株)日立製作所にもアドバイスを頂いている。