1. はじめに
永戸ら('98秋B110)は1997年1月に九州西方海上に発生した筋状層積雲について,気象研究所非静力学モデル(MRI-NHM)を用いて再現実験を行い,航空機観測データとの比較などから現実の雲の様子を良く再現していることを示した.今回は,前回の実験より細かい水平分解能での実験結果を示し,雲の形成に寄与する混合層内の鉛直循環について解析をした結果について報告する.
2. 数値実験の概要
実験はMRI-NHMを用い,前回とほぼ同様に行ったが,計算機の性能向上に伴い,格子数は300x300x38(前回は122x122x38),水平格子間隔は1km(前回は2km)とした.図2にMRI-NHMによる鉛直積算雲水量(LWP)の9時間予報値を示す.ほぼ同時刻のGMS-5の可視画像(図1)と比較すると,特に九州と五島列島の間から伸びる3本の雲列がMRI-NHMでよく再現されていることがわかる.
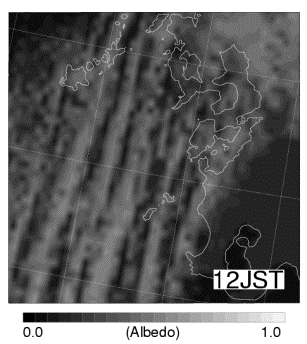
図1:1997年1月22日12JSTのGMS-5可視画像
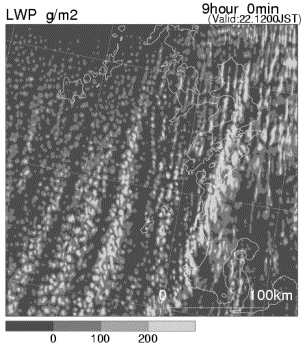
図2:MRI-NHMで計算されたLWPの水平分布.時刻は図1とほぼ同じ
3. 混合層内の鉛直循環
寒気の吹出しに伴い混合層が発達し,図2の時点では混合層内には高度約0.5kmに鉛直風振幅のピークを持ち,高度約1kmまで及ぶ鉛直循環が存在していた.ここでは水平規模が約10km以下のセル状循環が卓越しているが,それ以上の水平規模の循環を検出するために,振幅の大きい高度約0.5kmにおける鉛直風について,水平方向に20kmの移動平均をとり,水平規模20km以下(WS)とそれ以上(WL)の成分に分離した.このうちWL成分(図3)からは,南北方向に伸び,東西方向に約30kmの水平規模を持つロール状の振動が見て取れる.これは上昇・下降域がそれぞれ雲域と雲のない領域に対応しており,雲列の形成に大きく寄与している循環であることが示唆される.それぞれの成分のバリアンスをとって領域平均した結果, WLはWSの約1割程度の振幅を持つことがわかった.
ここで検出されたロール状循環の成因を調べるために,いくつかの感度実験を行った.このうち五島列島や長崎県西部(130E以西)の地形を除去した実験ではロール状循環は現れず(図4),雲列も再現されなかった.このことから,これらの地形効果がロール状循環の形成に寄与していることが示唆される.
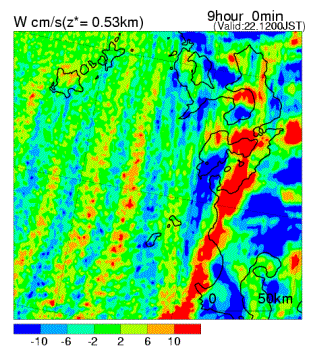
図3:高度約0.5kmにおける水平規模20km以上の鉛直風の水平分布.
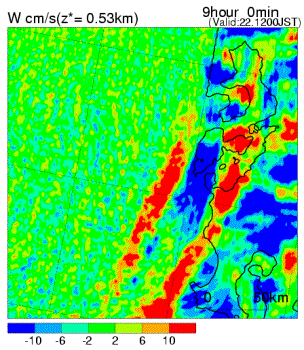
図4:図3と同じ.ただし,130E以西の地形を除去した実験.
4. まとめ
今回解析した筋状層積雲を含む混合層内には2種類の鉛直循環が存在していた.1つは水平規模約10km以下の強いセル状循環で,もう一つは.水平規模約30kmの弱いロール状循環である.後者は筋状雲の形状決定に寄与し,さらに感度実験から地形の影響を受けて駆動されていることも示唆された.